幼少期から小学生のうちに図鑑と触れ合うことの重要性 おすすめ図鑑
Last Updated on 2024年4月29日 by toshi
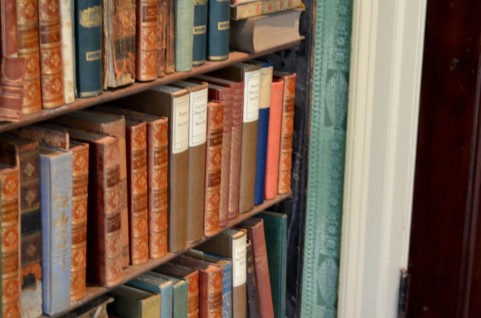
小学校の頃に勉強もできてそのまま伸びること、伸び悩んでしまう子その違いはどこにあるのでしょうか?
子供の頃どんなことをするのが好きだったかという質問に対して一つの共通点が浮かび上がってきました。
それは成績が伸びていた子供は幼い頃から 時間が好きでよく見ていたということです。
東大に受かるような子でも同じような傾向があります。
ちなみに、子供の時東大生が見ていた図鑑は、花や植物、動物、鳥、昆虫、乗り物、宇宙などと様々でした。
ただ、成績の良い子は、字が読めるか読めないかの幼いうちから図鑑が家にあったと言います。
ただ時間が家にあると言っても 全ての子供が成績が良いわけではありません。図鑑がうちにあっても 成績が悪い子はいます これはどういったことでしょうか?
今回は、図鑑について紹介していきたいと思います。
親の役割
ここで重要になるのは親の役割です。
伸びる子の親は、図鑑を使って子供の好奇心を伸ばすという役割を果たしていました。
具体的に言えば、子供が掴んでいる知識と現実世界の体験等親が結びつけることです。
例えば、乗り物の図鑑を見た後、電車に興味を持ったら実物を見に駅まで連れて行く、公園で花を見つけたら実際に図鑑でその花を探してみる、そうやって子供の中で図鑑と現実体験が結びつくと、子供のワクワク感は大きくなり知ることに純粋な喜びや楽しさを感じます。
それがより強い刺激となって脳に成長をもたるものをもたらすのです。
こうやって楽しく学ぶことができれば 机に長時間向かわなくても良い成績が取れるわけです。
脳は図鑑が育てる
次に、図鑑が脳にもたらす影響を考えてみましょう。本を読むときは脳の中でも言語野と呼ばれる、側頭葉や前頭葉などの部分が活性化します。
それに加えて図鑑は、必ず写真やイラストを伴いますから、図形認識や空間認知を担う領域など言語や以外の複数の脳の領域も同時に活性化できます。
図鑑はいつから読む
子供が3、4歳ぐらいになるとどんなことに対しても なぜ、どうしてというようになるというのはよく知られていますね。
このなぜなぜを一時期のものにせず、 いつまでもあらゆる物事に対して疑問を持ってるようにしてあげることが大事です。
この強い好奇心を少しでも早く子供に身につけてあげましょう。
図鑑を与える時期で言うと遅くとも3、4歳までには用意してあげて欲しいです。
これは男の子でも女の子でも共通です。
なぜそうしたいかと言うと それが脳の仕組みにあります。
多くの子供は3、4歳くらいになると徐々に好き嫌いを自分で判断するようになっていきます。
せっかく図鑑を与えても、図鑑は嫌いと言われてしまうかもしれません。 反対にその前から身近にあったものは自然に好きという判断をします。
その一番わかりやすい例が幼なじみでしょう。
子供と図鑑の関係も同じです。
面白い、面白くないと子供が自分で判断する前に親しんでいた時間を好きになる可能性が高くなります。
なので 好奇心をより豊かに伸ばしてあげるためには3、4歳を迎えるまでの期間が大切です。
5歳以上の子を図鑑に夢中にさせる方法
子供があまり図鑑に興味を示さなかったり 5歳になるまでに時間を与えることができなくて、図鑑は嫌いと言われてしまうこともあります。
もしそうだとしても、子供が嫌いだと言ったその図鑑を親が楽しそうに読んでいれば子供は興味を持ちます。
最初はただ親の真似をしているだけかもしれませんが、図鑑に書かれていることを話題にして話をしてあげると自然に内容への興味が湧いてきますので、心配は要りません。
脳の刺激という面だけで考えても、図鑑は子供の脳にいいということがわかるでしょう。
図鑑は知識を増やす
図鑑の最大の特徴は、パッと見てゾウやシカなどの大きさを体感できる工夫がされていることです。
最近の図鑑は非常によくできていて、情報をただ網羅しているだけではなく、小さな子供でもパッと見てわかる視覚的な仕掛けが満載です。
文字が読めなくても、写真やイラスト、色使いやレイアウトの工夫、子供向けと侮れないレベルの高さは脱帽ものです。
図鑑の役割は、何かを調べるもの、調べて覚えるためのものと思われがちですが、いきなりその段階に行こうとせず、最初はただ眺めているというのが正しい使い方です。
成長の初期の段階で、親が子供に教えてあげたいのは、世の中にはたくさんのものがあるということです。
幅広い知識が、子供の地頭を良くし学校での勉強の下支えになります。
また、図鑑の文章は、子供の理解やレベルに合わせた行為を厳選し、作成されています。
好奇心を広げて知識を増やしてくれるだけでなく、知らず知らずのうちに言語に対する感覚も刺激してくれるのです。
図鑑を見ているだけで知っている言葉や漢字がどんどん増えていくでしょう。
幼少期 おすすめ図鑑
0歳から4歳 子供図鑑英語付き
 |
![]()
学研の幼児向け図鑑です。
動物、乗り物体など子供が好きなジャンル別に名前や形をイラストで紹介。これなんだ、どれがいいなどと親子で会話しながら言葉が増えるでしょう。
1から100までの絵本
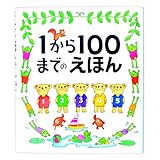 |
![]()
愉快なお話を読みながら1から100までの数を実際に数えて覚えることができる絵本。
20種類以上の動物が登場し、指をさしながら数を確認したくなります。
最初は、絵本図鑑を利用する
いきなり図鑑デビューする子や、図鑑に見向きもしない子供たちの関心を図鑑に向けるためには、図鑑を面白いと思ってくれるかどうかが重要です。
まず、図鑑に慣れるステップでは、絵本を読み聞かせてあげる感覚で楽しみながら読むのがベストです。
それでは、自然科学系のおすすめ絵本図鑑を紹介します。
人体絵本 めくってわかる体の仕組み
 |
![]()
体の内部の仕組みと働きをリアルなイラストと仕掛けを使って解説したい絵本。胸の仕掛けをめくると、胸骨、肋骨筋肉が現れて体の奥までよく見えます。
小学館 図鑑 neo 本物の大きさ 絵本 健生代 水族館
 |
![]()
サメやハリセンボンなど海に生息する生き物の姿を本物の大きさで紹介した迫力満点の図鑑です。
それぞれの魚の特徴を分かりやすい言葉で楽しく紹介しています。
楽しみながら 図鑑を遊び尽くす おすすめ図鑑
それではいよいよ図鑑に親しむステップです。
図鑑と言っても色々な会社から出版されているので、おすすめの図鑑を紹介していきたいと思います。
小学館の図鑑ネオシリーズ
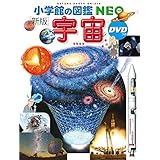 |
![]()
星座、宇宙に関する情報量がたっぷり詰まった図鑑。
ドラえもんが案内するDVDも分かりやすく、楽しく勉強することができます。
解説ページも 面白く、飽きっぽい小学生でも飽きずに勉強することができます。
小学館の図鑑 NEOシリーズには、 その他にも動物 植物、化学の実験など多くの図鑑が出版されていますので、シリーズで揃えるのもいいかもしれませんね
講談社の動く図鑑 MOVE シリーズ
 |
![]()
印象的な写真が豊富で見るだけでも楽しい図鑑。もちろん、NHK制作のDVDも見応えがあります。 思わず、博物館に行きたく なってしまうような魅力のある図鑑です。

